このサイトはアフィリエイト広告を利用しております
因習村の祟りと笑いが交錯する!Group SNEの妄想系言い訳ゲームが再び登場
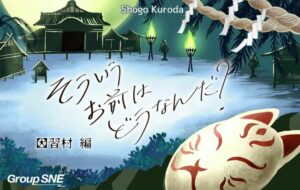
2025年12月5日、Group SNEが贈る人気シリーズ最新作『そういうお前はどうなんだ? 因習村編』が登場。舞台は祟りと伝承が残る山奥の“因習村”。祭りの翌日、惨劇が起き、容疑者たちは妄想と口八丁で互いを吊るし上げる!犯人を当てる推理ゲームではなく、「どう言い訳するか」を競う会話型パーティーゲームです。誰もが笑いながら即興で物語を紡ぎ、言葉の応酬が生むカオスな展開に夢中必至。シリーズ特有の狂気と笑いがさらに進化した、短時間で盛り上がる傑作コミュニケーションボードゲームです。
第1章 作品概要と基本情報
「2025年12月5日発売!『そういうお前はどうなんだ? 因習村編』とは」
2025年12月5日に発売される『そういうお前はどうなんだ? 因習村編』は、人気シリーズ最新作となる“妄想系言い訳コミュニケーションゲーム”です。舞台は、古い風習が残る山奥の村「因習村」。祭りの翌日に起きた殺人事件をきっかけに、容疑者同士が互いを疑い、妄想と口八丁で犯人を押し付け合うのが本作の醍醐味です。推理力ではなく「言い訳力」が試されるという独自のゲーム性で、前作以上のカオスな盛り上がりを見せます。
「Group SNEが贈る“妄想系言い訳バトル”シリーズの最新作」
本作を手がけるのは、テーブルトークRPGやボードゲームで知られるGroup SNE。シリーズ特有の「ミステリー×大喜利」構成を踏襲しつつ、今回はよりドラマ性を重視した物語演出が特徴です。前作から好評だった“即興で物語を作る感覚”を残しつつ、因習や祟りといったホラー要素を融合。プレイヤーが創作的な嘘をつくほど場が盛り上がる、笑いと狂気の境界線を楽しめる異色のタイトルです。
「対象年齢12歳以上/プレイ人数3〜6人/プレイ時間20分」
『因習村編』は、3〜6人のプレイに対応し、1ゲーム約20分で遊べるテンポの良さが魅力です。対象年齢は12歳以上で、家族や友人同士、パーティーゲームとしても最適。ルールが直感的で、初プレイでも5分で理解できる構成となっています。発想力・言葉の瞬発力・場の空気の読み方など、プレイヤーの性格が反映されやすく、毎回違う展開が生まれるのもポイントです。
「前作との関係:単体で遊べる独立タイトル」
本作はシリーズの続編でありながら、単体で完結する独立作品です。『そういうお前はどうなんだ?(初代)』や『街角編』『温泉編』などとは混ぜて遊べませんが、共通する“弁明して乗り切る”ゲーム性は健在。過去作を知らなくても問題なく楽しめる設計で、初心者にも入りやすい構成です。むしろ今作から始めるプレイヤーも多く、シリーズの“新しい入口”として機能しています。
「黒田尚吾×ちゅぱみによる制作チーム紹介」
デザインを手がけるのは黒田尚吾氏。緻密なゲームバランスと笑いのセンスを融合させた構成力が高く評価されています。イラストはシリーズおなじみのちゅぱみ氏が担当。独特のタッチで描かれるキャラクターたちは、怪しげでどこかユーモラス。プレイヤーの妄想を刺激する絵柄で、ゲームの世界観に深みを与えています。両者のタッグによって、因習×笑いという絶妙なトーンが完成しました。
第2章 テーマ・世界観・ストーリー
「舞台は“因習村”――祟りと祭りが渦巻く日本的ホラー風土」
物語の舞台は、山深くにある「因習村」。古くから祀られる祠(ほこら)と奇妙な祭りが伝わる村で、怪しい風習と閉鎖的な人間関係が息づいています。プレイヤーは事件の容疑者となり、村人同士で犯人を押し付け合うことに。祟りや伝承、村の掟など、典型的な“日本的ホラー”の要素を取り入れつつ、笑いに昇華させたバランス感覚が秀逸です。
「“祠の祟り”と殺人事件:導入ストーリーの全貌」
祭りの翌朝、村人の一人が無残な姿で発見される。
「これは……祠を壊した祟りじゃ!!」
そんなセリフから始まる混沌の物語。だが村の住人たちは推理能力ゼロ、妄想と弁明だけは超一流。プレイヤーは“怪しい村人”として即興で言い訳を繰り広げ、最も怪しい者を吊るし上げます。事件解決ではなく“責任のなすりつけ合い”がテーマの、風変わりでユーモラスなミステリーゲームです。
「伝承・儀式・祭りの要素がゲーム体験に与える影響」
因習村の設定には、神話的な“祟りの因果”が随所に散りばめられています。
プレイヤーが語る妄想に祭りや伝承を組み込むと、説得力や面白さが倍増。
「俺は祠を壊してない!あれは山の神のせいだ!」など、即興劇のような会話がゲームを彩ります。
伝統的テーマを舞台に“笑い”を生む構成は、Group SNEならではの秀逸な脚本設計です。
「登場人物(容疑者)たちの設定とキャラクター性」
登場する村人は、それぞれ濃いキャラクター設定を持っています。
村長、巫女、猟師、旅人、学者など、多様な背景を活かして言い訳を展開。
誰が本当のことを言っているのかよりも、“誰が一番面白い言い訳をするか”が勝負の分かれ目。
キャラクターのロールプレイを強調する設計により、毎回違う物語が生まれるリプレイ性も抜群です。
「ミステリー×コミュニケーションの融合演出」
『因習村編』は、推理ゲームでありながら、実際には会話劇=コミュニケーションが中心。
“口八丁で相手を納得させる”ことが目的で、論理性より勢いが求められます。
プレイヤー同士の駆け引き、嘘をつく快感、暴走する妄想──その全てが笑いと緊張を生む。
ミステリーを題材にしつつも、最終的には人間関係と心理戦が楽しめる構造になっています。
第3章 ゲームの目的と遊び方
「ゲームの流れ:妄想→弁明→吊るし上げ→決着」
1プレイはおよそ20分。プレイヤーは事件発生後の村人となり、順番に“自分の妄想ストーリー”を披露します。
他のプレイヤーはその言い訳を論破したり、矛盾を突いたりしながら混乱を拡大。
最終的に“最も怪しい者”を全員で投票し、村の座敷牢へ送り込む──それが勝敗の決め方です。
ルールは簡単ですが、発言の内容次第で勝敗が大きく変わるため、会話のセンスが光ります。
「犯人探しではなく“言い訳バトル”が主題」
通常のミステリーゲームは“真犯人を見つける”のが目的ですが、本作は真逆。
むしろ自分が犯人にされないよう、いかに上手く言い訳できるかが勝負です。
自分の立場を正当化するための創作・妄想・話術が求められ、プレイヤーによってまったく異なる展開になります。
いわば「即興演技+論破+大喜利」を混ぜたようなゲーム性で、毎回新しい笑いが生まれます。
「ラウンド制と投票システムの概要」
ゲームは複数ラウンドで進行し、各プレイヤーが順番に弁明や質問を行います。
全員の話が出揃った後、もっとも“怪しい”と思う人物に投票。
最も票を集めたプレイヤーが“座敷牢行き”となり、一定数の票を得たプレイヤーが敗北します。
論理よりも“ノリ”で投票が決まることも多く、緊張と笑いのバランスが絶妙です。
「ポイント制ではなく“場の空気”で勝負する心理戦」
本作にスコアや明確な勝点は存在しません。重要なのは、その場の空気を支配できるかどうか。
発言のテンポ、他人との掛け合い、タイミングの妙──すべてが勝敗を左右します。
つまり勝ち負けよりも“盛り上げた者が勝者”という文化的ルールが生まれるのです。
まさにパーティーゲームの本質を体現した、心理的駆け引き型ゲームです。
「短時間でも白熱する設計の秘密」
20分という短いプレイ時間でも、1人ひとりが強く印象に残る構成が秀逸です。
ラウンドごとに緊張感と笑いの波があり、1プレイ終える頃には自然と再戦が始まる中毒性。
テンポの良いターン進行とシンプルな発言構造により、初心者でもすぐに没入できます。
「短いのに深い」「軽いのに濃い」――これが“因習村編”の真骨頂です。
第4章 コンポーネントと構成物
「カード内容一覧とアイコンの意味」
『因習村編』に含まれるカードは、登場人物・お題・状況・儀式など、物語を形成する要素で構成されています。
各カードにはシンプルなアイコンが描かれ、祭り・祠・血痕などを象徴。プレイヤーはこれらを自由に解釈し、即興で物語を語ります。
この“曖昧な指示”こそが妄想を誘発し、会話を自然に盛り上げる鍵。明確な指示よりも想像の余地を残す設計が、作品の完成度を高めています。
「因習村テーマカード・役割カード・イベントカードの役割」
カード構成は3種類。テーマカードで物語の方向性を決定し、役割カードでキャラ立ちを付与、イベントカードで意外な展開を演出します。
「祭りが中止になった」「祠が壊れた」などのイベントが発生するたび、村の空気が変化。
この構造がプレイヤー間のやり取りをドラマチックに変化させ、即興演劇のような体験を生み出します。
「箱サイズ・材質・収納方法」
箱はコンパクトサイズで持ち運びしやすく、紙製ながら厚みのあるしっかりした作り。
カードは耐久性のあるコート紙仕様で、長時間の使用でも痛みにくいのが特徴です。
収納はシンプルで、カードを束ねて入れるだけ。旅行先やイベントにも持ち込みやすく、“短時間×携帯性”を重視したデザインです。
「ミニ拡張『祭り』カードの内容と使い方」
『因習村編』には、拡張カード「祭り」が同梱。これはゲーム中に混沌と笑いを呼ぶ“特殊イベント”を追加する要素です。
このカードを引いた瞬間、ルールが変化したり、全員が儀式を即興で再現したりと、場が爆発的に盛り上がります。
物語に厚みを加えるだけでなく、プレイヤー同士の関係性も崩すスパイスとして機能。上級者向けにおすすめの要素です。
「パッケージデザインとホラー演出の魅力」
外箱のデザインは“和風ホラー×レトロ祭り”をテーマに、墨色と朱色を基調とした印象的な構成。
ちゅぱみ氏のイラストによる村人たちの表情はどこか不気味で、コメディホラーの雰囲気を完璧に再現しています。
恐怖と笑いのバランスが絶妙で、棚に並べるだけで“ボドゲ棚映え”する美しいパッケージです。
第5章 プレイ体験と面白さの本質
「なぜ推理ではなく“妄想”なのか? 独自のゲーム哲学」
『因習村編』が他のミステリー系ゲームと決定的に異なるのは、目的が“真相解明”ではなく“創造的混乱”であること。
プレイヤーは正解を探さず、嘘を創り、説得力で勝負します。
つまり、想像力と会話力こそが武器。推理のロジックよりも感情の勢いが重要で、想定外の展開こそがこのゲームの核心です。
「会話が爆発的に盛り上がる“因習×言い訳”構造」
「祠を壊したのは俺じゃない!」「じゃああの夜、どこにいたんだ?」
——そんなやり取りが自然に生まれるのが『因習村編』の魅力。
ホラーな題材とコメディ要素が融合し、笑いと緊張の両方を味わえます。
一見シンプルなカードゲームながら、プレイヤーの個性によってまるで即興芝居のような展開に変化する奥深さがあります。
「1プレイ20分のテンポ設計とリプレイ性」
1プレイ20分という短さながら、内容は非常に濃密。
毎回テーマカードの組み合わせが変わるため、何度遊んでも新しいドラマが生まれます。
プレイヤーの発想や口調次第で雰囲気が変化し、同じ展開は二度と起きません。
リプレイ性の高さはパーティーゲームとしても優秀で、“短くても記憶に残る”名作です。
「初見プレイヤーでも笑いが生まれる仕掛け」
初心者でも楽しめるよう、カード内容は誰でも想像しやすい言葉で設計されています。
「祟り」「村人」「夜」「秘密」など、連想しやすいワードばかり。
これにより、初対面の人同士でも自然に会話が弾み、緊張がほぐれる効果があります。
ボドゲ初心者の導入にも最適で、“笑って仲良くなるきっかけゲーム”としても人気です。
「シリーズ特有の“口八丁戦略”を極めるコツ」
勝つためには論理ではなく“勢いと物語力”が重要。
他人の発言に瞬時に乗り、笑いを生む返答をすることで票を集めにくくできます。
また、あえて自分を怪しく見せ、別のプレイヤーを巻き込む戦法も有効。
この「場の支配」と「ネタの瞬発力」を極めることが、真の“因習村マスター”への道です。
第6章 戦略・心理戦・言い訳テクニック
「初手で疑われた時の“切り返し”テクニック」
最初に疑われたプレイヤーはチャンスです。慌てず“笑える言い訳”で返せば、一気に流れを変えられます。
例:「違う!俺は祭りの準備で忙しかったんだ!」といった村の生活感を混ぜた発言が有効。
真面目に否定するよりも、状況を物語化する方が信憑性と面白さが増します。
「他人の言い訳に乗る“便乗型スタイル”の強み」
他プレイヤーの妄想を拾って物語を拡張するのも強力な戦法。
「確かに!俺もその夜、祠の近くで光を見た!」など、共感しつつ情報を盛ると、自分への疑いをそらせます。
協力と裏切りが混ざるこの駆け引きが、『因習村編』の心理的スリルを最大化します。
「沈黙が逆効果? 発言バランスの心理的駆け引き」
発言が少なすぎると「隠している」と疑われ、喋りすぎても「焦っている」と見なされます。
最適なのは“テンポの良い一言+余白”のリズム。
他人に考える余地を与えながら自分の立場を守るバランスが、勝敗を分ける要素です。
「“裏切り者を座敷牢にぶち込む”瞬間の演出」
最終投票で追い詰められたプレイヤーを“座敷牢行き”にする瞬間は、本作の最大の山場。
笑いと緊張が頂点に達し、全員が拍手や悲鳴で盛り上がります。
このカタルシスが中毒的で、プレイヤーが何度も再戦したくなる理由です。
「上級者向け:キャラづくりとセリフ演出で勝つ方法」
上級者は、キャラを演じ切ることで場を制します。
「偏屈な村長」「冷静な学者」「怪しい旅人」など、役割を作り込むと物語が濃密に。
セリフに抑揚をつけ、感情を演出することで他人の投票を操作する――
それはもはや演技と心理戦の融合。これが“因習村編”を芸術に昇華させる極意です。
第7章 シリーズ比較・進化ポイント
「『街角編』『温泉編』との違いと共通点」
過去作『街角編』『温泉編』と比較すると、『因習村編』はテーマ性がより“ドラマ的”です。
前作が日常の中の嘘を笑う内容だったのに対し、今作は祟りや村の掟など、非日常要素を導入。
共通点は「妄想と言い訳で物語を動かす」基本構造ですが、ホラー要素が加わったことで“物語性の厚み”が格段に増しています。
「“因習村”がもたらすホラーテイストの強化」
舞台を山奥の閉鎖空間に設定することで、発言の一つひとつが重く響きます。
祠・祭り・村八分などのワードが自然と緊張感を生み、笑いの中にも不気味さが漂う。
このギャップがプレイヤーを引き込み、単なるギャグゲームでは終わらない“物語的ホラー”を体験できます。
「演出カードとセリフテンプレートの刷新」
本作では、プレイヤーが即興で話しやすいように「セリフ補助カード」が改良されています。
「その夜、私は…」「祠の中で見たのは…」など、語りの導入を支える構文が多く、初心者でも自然にロールプレイ可能。
シリーズの中で最も“喋りやすい”“入りやすい”作品と評されています。
「ゲームデザイン上の改善点とテンポアップ」
従来よりもラウンド数が調整され、1プレイ20分の中で濃い展開を描けるよう最適化。
テンポの良い進行と場の盛り上げを両立し、プレイヤーが飽きる瞬間を作らない構成です。
特に弁明フェーズの制限時間ルールが絶妙で、“盛り上がるちょうど良さ”を実現しています。
「ファンが語る“シリーズ史上最高の狂気”」
SNS上では「シリーズ中もっともカオス」「全員が裏切り者」「RPが止まらない」と話題。
因習・祟り・言い訳という不穏なテーマが、笑いと恐怖を融合させています。
“笑いながら震える”という、他にはない感情を味わえるのが『因習村編』最大の魅力です。
第8章 拡張と遊び方バリエーション
「ミニ拡張『祭り』カードの詳細と導入方法」
拡張カード「祭り」は、ゲーム中の特定タイミングで挿入され、場の雰囲気を一変させます。
“全員が同時に踊り出す”“祠を再建しろ”など、突発イベントが発生し、即興芝居が加速。
導入は簡単で、基本デッキに数枚混ぜるだけ。慣れたプレイヤーほど爆笑必至の展開になります。
「お題カードの追加・自作ルールで広がる遊び方」
プレイヤー同士でオリジナルお題カードを作るのも人気の遊び方。
「村の禁忌」「夜中の声」「神の怒り」など、自作テーマを入れるだけで新鮮な展開が生まれます。
この柔軟性の高さがシリーズの魅力で、ファンコミュニティでは“自作拡張祭り”が恒例行事になっています。
「オンライン通話・ボイスチャットで遊ぶコツ」
『因習村編』は会話中心のため、ボイスチャットとの相性も抜群。
ZoomやDiscordを使えば、遠隔でも村会議の臨場感を再現可能です。
背景画像を“夜の村”に設定すれば没入感も倍増。オンラインボドゲ会で最も盛り上がるタイトルの一つです。
「“ハウスルール”で変化するプレイ体験」
プレイヤー独自のルール追加も推奨されています。
たとえば「最も面白かった言い訳を表彰」「吊るされた人の祟りルール」など。
公式ルールに縛られず、即興で物語を広げる自由度が本作の真価です。
「繰り返し遊べる理由とマンネリ防止テク」
カードの組み合わせが膨大なため、遊ぶたびに新展開が生まれます。
さらにプレイヤーのキャラ性・トーン・発想で雰囲気が変化。
定期的に“祟り縛り”“祭り縛り”などのテーマ縛りを設定すると、飽きずに長く遊べます。
第9章 対象プレイヤーとシーン別おすすめ
「家族で遊べる? 12歳以上のバランス設定」
12歳以上推奨とされていますが、実際は中学生以上なら十分に楽しめます。
ホラー要素はコミカルに描かれており、恐怖より笑いが中心。
親子や兄弟、学生グループにも安心しておすすめできます。
「友人・飲み会・パーティー向けの盛り上げ方」
本作は笑いが連鎖しやすく、飲み会やパーティーでの使用率が高いゲーム。
テンポが良く、短時間で盛り上がるため、アイスブレイクにも最適です。
勝敗よりも“誰が一番面白いか”を競うことで一体感が生まれます。
「ボードゲーマー層に刺さる“軽量系ミステリー”」
ガチ勢にも人気なのは、“推理しないミステリー”という逆転構造の妙。
考えるより感じる、理屈より演出。そこに深みがあると評価されています。
重ゲーの合間にプレイする“笑いの箸休め”としての価値も高いです。
「心理戦が苦手でも楽しめる要素分析」
戦略より即興が重視されるため、頭脳戦が苦手な人でも大丈夫。
相手を出し抜くより、笑わせた者が勝つ。そんな“場の空気ゲー”です。
一人の暴走が全員を笑わせることもあり、失敗すら成功に変わる構造です。
「即興力・発想力を鍛える教育的側面」
創造力・言語力・柔軟な思考を育む“コミュニケーション訓練”としても優秀。
演劇部・表現系サークル・教育現場でも採用例があり、
「即興力トレーニング教材」としての評価も高まっています。
第10章 レビュー・評価・SNSトレンド
「実際に遊んだプレイヤーの口コミと感想」
プレイヤーからは「腹筋崩壊レベル」「毎回展開が違う」「全員が狂う」と高評価。
ホラー題材なのに笑える、というギャップが絶賛されています。
特に“言い訳しながら罪をなすりつける瞬間”のカタルシスは唯一無二。
「X(Twitter)・YouTubeでの人気動画・実況配信」
YouTubeでは開封・プレイ動画が急増し、実況配信では“笑ってはいけない因習村会議”が人気企画に。
ハッシュタグ「#そういうお前因習村」で検索すると、笑撃の言い訳名場面が多数投稿されています。
「ファンアート・二次創作の盛り上がり」
ちゅぱみ氏のイラストをもとにしたファンアートも活発。
祠や祭りをテーマにした創作が相次ぎ、ボドゲを超えた“物語文化”として拡散しています。
「ショップ店員・レビュアーの総評」
ボードゲーム専門店では「初心者もベテランも笑える奇作」として売上上位にランクイン。
一部では“口八丁パーティーの新定番”と呼ばれるほどの存在感を放っています。
第11章 購入・予約・販売情報
「主要販売店(Amazon/あみあみ/ボドゲーマ/ヨドバシ)」
Amazonやあみあみ、ボドゲーマなどで予約受付中。
店頭では早期完売が見込まれており、発売日(12月5日)前にの確保がおすすめ。
「価格・入荷時期・在庫状況比較」
定価は約2,200円(税込)。オンライン店舗では割引販売もあり。
軽量箱ボドゲとしてはコスパが非常に良く、プレゼント需要も高い。
「予約特典・初回生産分の違い」
初回生産分には、特製ステッカーやPRカードが付く店舗も。
Group SNE公式通販では限定アクリルスタンド同梱セットも用意されています。
「プレゼント用途・ギフト需要の高まり」
パッケージがスタイリッシュなため、ボドゲギフトにも最適。
“笑って楽しむホラー”というテーマは季節行事(ハロウィンなど)とも好相性です。
「再販・流通予定と品薄リスク」
Group SNE作品は小ロット生産のため、再販まで数ヶ月空く場合があります。
気になる人は初版確保が鉄則。再販時には仕様変更の可能性も。
第12章 総括・おすすめ購入ガイド
「こんな人におすすめ!プレイヤータイプ別ガイド」
-
初心者層:簡単ルールで初対面でも笑える。
-
中級者層:即興・RP好きに最適。
-
上級者層:キャラ演技・心理戦を極めたい人向け。
幅広い層が笑って楽しめる“万能型コミュニケーションゲーム”です。
「シリーズファンが語る“因習村編の完成度”」
ファンの多くが「シリーズ中、最も完成度が高い」と評価。
テーマ・演出・テンポの三拍子が揃った傑作。
ホラーと笑いのバランスが絶妙で、Group SNEの実力を再確認させる作品です。
「笑いと狂気の境界線を描く傑作パーティーゲーム」
『そういうお前はどうなんだ? 因習村編』は、“笑えるホラー”という新ジャンルを確立した存在。
会話・演技・想像力が融合した構造は、他のボドゲにはない体験を提供します。
「ボードゲーム初心者にも勧められる理由」
ルールが直感的で、失敗しても笑いになるデザイン。
人見知りでも自然に会話でき、パーティーや合宿での定番タイトルになりそうです。
「まとめ:因習と妄想の果てに、あなたは何を信じるか?」
“犯人を探すのではなく、笑いながら物語を作る”――
それが『因習村編』の本質。妄想と会話が交錯する瞬間、あなたの中の語り部が目を覚ます。
信じるか、疑うか。最後に笑うのは、最も口の上手い“お前”だ。
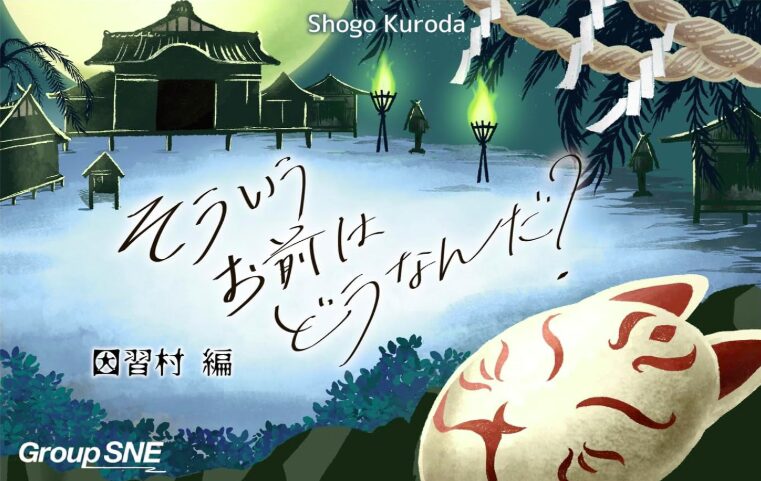



コメント